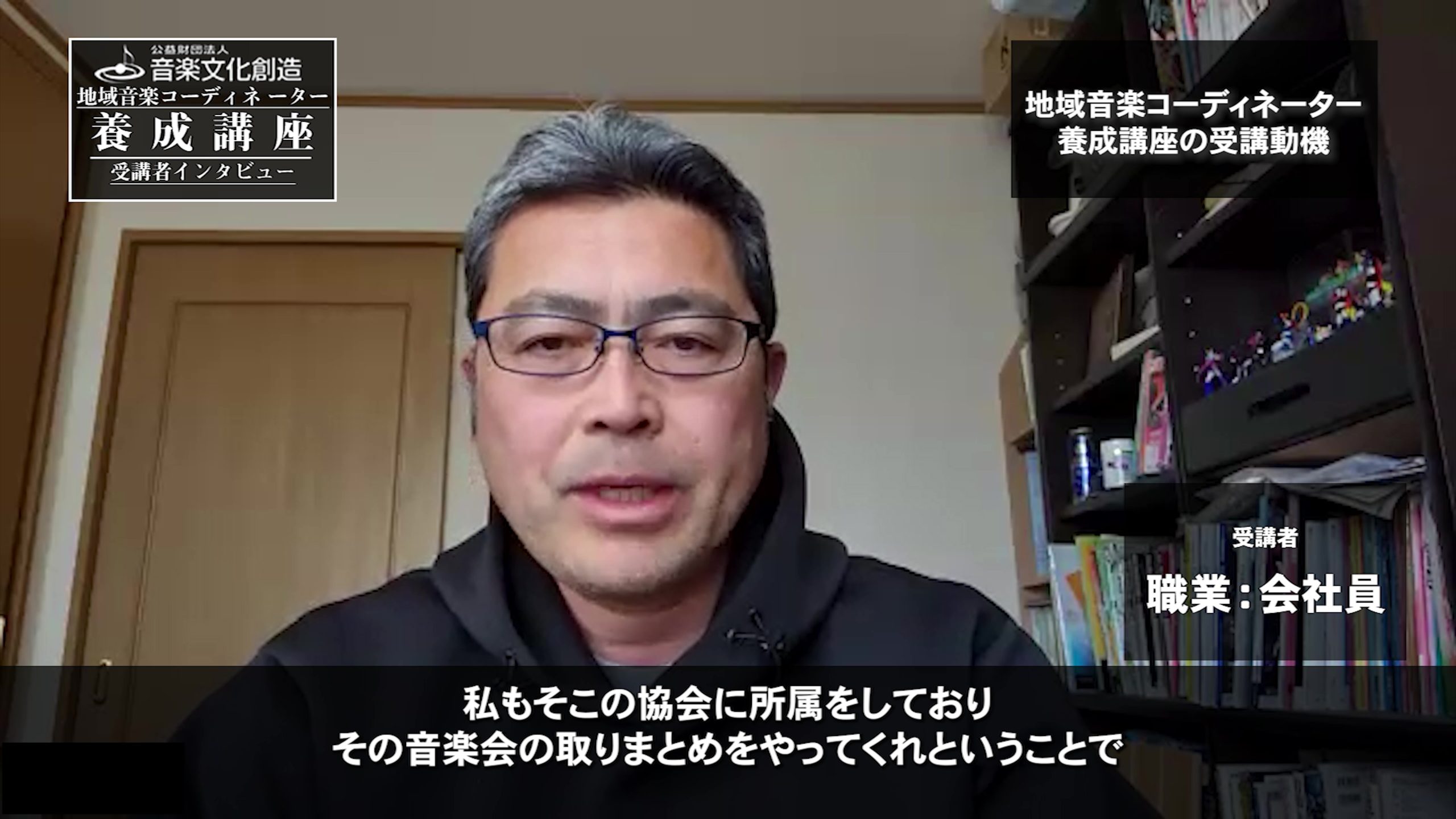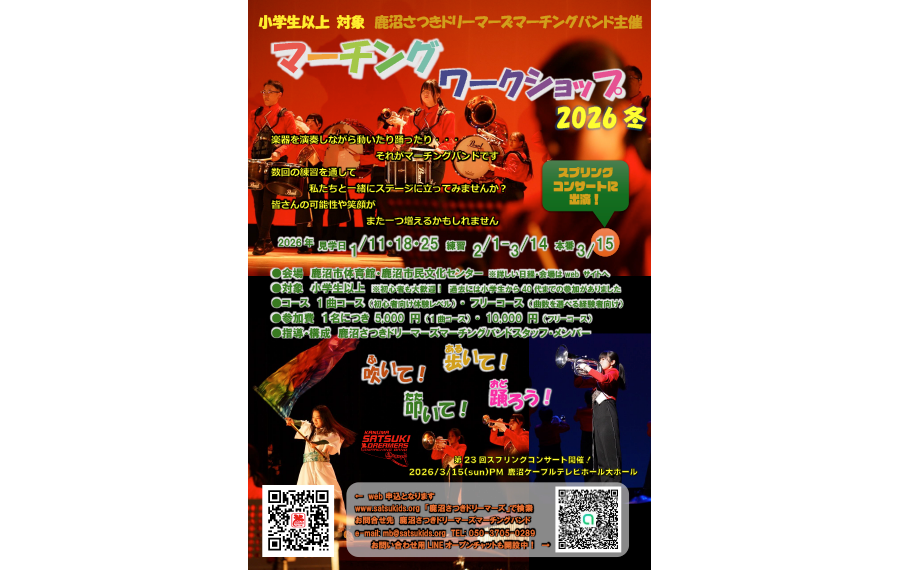地域音楽コーディネーター 社会福祉法人職員 大阪府 市原亜希子さん

- ■活動テーマ:
- 歌って笑ってリズムにのって〜脳も体も健康に
- ■目次:
- ■活動開始時期:
- 2009年~現在
- ■場所:
- 高槻市内
- ■対象:
- 60代~80代
- ■活動内容
1.きっかけ
アクティブシニアが集う歌のサークルは、2009年に結成されました。代表会員の方からピアノ伴奏を依頼されたことがきっかけで、健康音楽指導士(*1)のピアノ伴奏者とリトミック担当の私が関わらせていただくことになりました。今年で16年目を迎えます。
*1)健康音楽指導士:日本音楽健康協会が認定した指導士。歌と音楽を活用して身体機能の改善・認知機能の予備を行う。
厚生労働省が打ち出している「人生100年時代」構想では、高齢者から若者まで全ての人が元気に活躍し続けられる社会を目指していますが、それを実現するためには心身ともに元気で生活できる健康寿命(2024年の健康寿命は男性が72.5歳、女性が75.5歳)が大切となります。その要素として、食生活・運動・そして「社会参加」と言われています。本サークルでは、会員同士で意見を出し合い、発表会に出演するかどうかを決めるなど、主体性を尊重する環境が作られており、音楽を通した「社会参加」の場になっていると考えます。
2.具体的な内容
(1)会員
現在15名の会員で、月1回、高槻市内で90分行っています。会員募集については、口コミやステージ発表を見て興味を持ってくださった方が入会されることが多いです。
(2)目標
歌のサークルでは、歌唱や楽器演奏の上達を目指すことよりも、心地よい発声の仕方を共有し、ハーモニー、フレーズ、リズム等を「頭(脳)」と「体」でバランスよく感じられるようになることを目指しており、手法のひとつとして「リトミック」を取り入れています。
(3)活動内容
ⅰ.発声練習~歌唱
まず健康音楽指導士による準備運動が始まります。メンバーが良く知っている文部科学省唱歌などを使って、発声練習を行います。口周りや体がほぐれてきたら、文部科学省唱歌(早春賦、村祭、小さい秋みつけた等)童謡(どんぐりころころ等)わらべうた(あんたがたどこさ等)フォークソング(学生時代、上を向いて歩こう等)そのときの季節に応じた曲を選んで歌います。
リズムに特徴のある曲、例えば文部科学省唱歌の「ゆき」という曲の弾むように歌う箇所(♪ゆきやこんこ、あられやこんこ)に手拍子をつけ、体でリズムを感じながら歌うこともあります。また輪唱、特定の言葉を抜いて歌う、4拍子の曲を3拍子に変えて歌うなど、脳と体をフル回転させながら音とリズムに触れていきます。
ⅱ.楽器演奏
休憩を挟んで、メロディベルやトライアングル、カスタネット、ミニキーボード等を使って演奏します。担当楽器のグループごとに、メンバー同士でリズムを考えて合奏することもあります。
ⅲ.歌唱
2度目の休憩を挟み、活動のエンディングはクールダウンの時間です。数曲を各々のペースで(声の大きさやリズムの正確さを求めず自由に)歌います。最後の曲は「今日の日はさようなら」が定番となっており、全員の拍手でその日の活動が終了します。
(4)活動を提供する際の留意点について
①安全性の確認
活動が安全にできるかを確認し、身体の状態(手足が動かしづらい等)に合わせて行います。(例:ある動きを控えめにする、別のやり方で行えるよう相談する等。)
②メンバー全員の主体性を尊重
音楽活動を行う上で、各々のメンバーがメニューを選び決定し、一定の役割を担うことで「楽しさ」と「今日も参加しようという意欲」につながります。例えば、私が活動の大枠を提案し、詳細はメンバーに考えてもらいます。また打楽器などを使う場合は、同じ楽器を担当するメンバー同士でリズムを作りあげ、全員で合奏するといったように、メンバーの主体性を尊重するようにしています。
キーボードの演奏にもチャレンジ!本番ではリトミックの手法を用いて、歌唱とリズム活動を披露しました。客席からは手拍子が湧き起こり、大変盛り上がりました。



3.成果と課題
(1)成果
定期的にメンバー同士が集まり、直接会ってコミュニケーションを図り、一緒に活動することで以下のような成果が得られています。
①本会を16年継続できたことは成果の一つです。月1回という無理のないスケジュールであったこと、メンバー全員の主体性を尊重し、できる範囲で役割を持ち、活動の方向性について一緒に考えながら全員で作る会にしてきたことが、継続の要因になっています。
②一緒に歌い、時には少し難しいリズムにもチャレンジし、うまくいってもいかなくても全員で大笑いすることにより、脳と身体がバランスよくほぐれる実感を持つことができ、健康増進につながっています。
(2)課題
本サークルは、活動場所に通えるアクティブシニアを対象としていますが、長く続けてこられたメンバーが、年齢を重ねられ少しずつ通うことがつらくなられているのではないかと懸念しています。実際に「元気な顔を見せられるうちに、さようならするわね」と言って退会される方もおられました。それぞれの価値観は尊重すべきですが、活動の本質が心身ともに元気で生活できる健康寿命を大切にする視点を持つことであるならば、通える間だけの活動と単純に割り切るのではなく、身体の状態に応じた場所、内容の工夫等を考えていく必要があるのではないかと感じています。
4.抱負
今後、以下のような活動を計画しています。
①主体的に社会参加できる場として歌のサークルを継続し、メンバー全員で楽しい活動にしていきます。
②新たなチャレンジ
私は、社会福祉法人の職員として障がいがある児童と、その保護者にかかわる仕事をしています。子ども自身は音楽が好きで、特に鍵盤楽器や打楽器に興味があるのに、ご本人に合う活動と場所が見つからないという声を保護者からよく耳にします。そこで、これまでの音楽経験を生かし、福祉サービスの視点を持ちながら、より自由度の高い、地域のインフォーマルな支援として、子どもから高齢者や障がいがある大人の方まで、本人のペースで楽しめるような音楽活動の場を作り上げていきます。
地域音楽コーディネーターや生涯学習音楽指導員として皆さまの活動を掲載しませんか?
活動紹介やイベント告知をご希望の方は、下記のページをご覧ください
音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。
詳しくは下記をご覧ください。