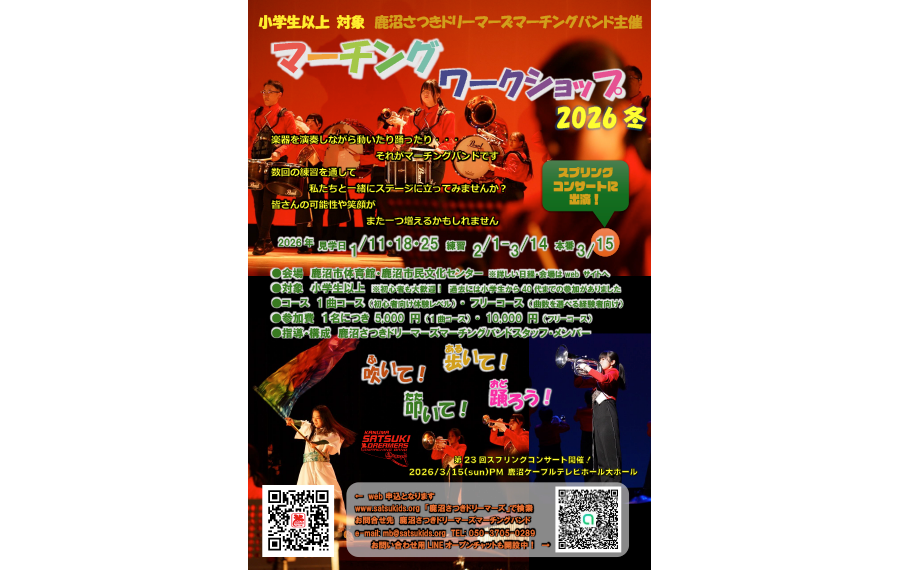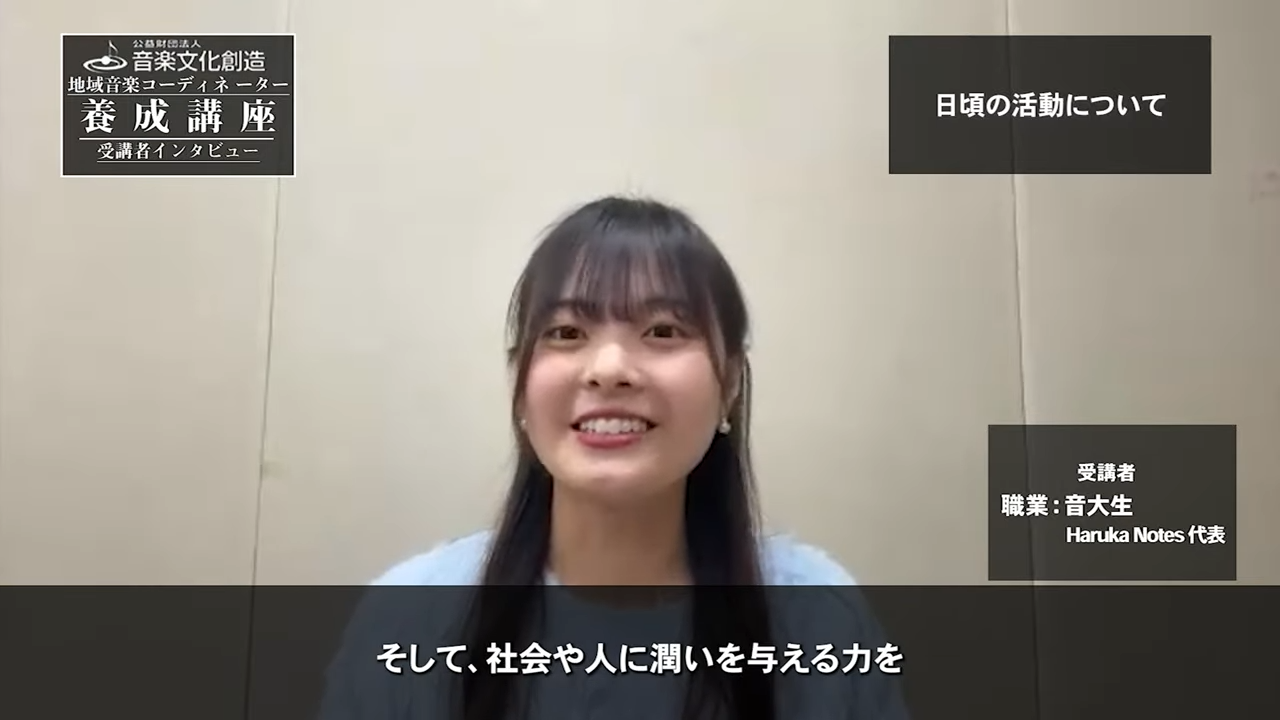地域音楽コーディネーター 元高校教師 神奈川県 佐野誠さん

- ■活動テーマ:
- 学校卒業後、いつでも音楽が出来る!~合奏イベントの運営を通じた「生涯音楽」活動の推進~
- ■目次:
- ■活動開始時期:
- 2021年~現在に至る
- ■場所:
- 神奈川県横浜市内のホール他
- ■対象:
- 一般
- ■活動内容
1.きっかけ
(1)「自由演奏会 in 本郷台」に参加
私は高校時代に吹奏楽部に在籍し、トロンボーンを演奏しておりました。しかし大学在学時代から高校教師として就職するまでの間、演奏活動をする時間が取れず、楽器に触れる機会が有りませんでした。2019年の秋、職場へ「自由演奏会 in 本郷台」(*1)のチラシが届いたことをきっかけに、演奏を再開しました。これは、音楽と楽器が好きな人は誰でも参加でき、その日集まった人がその場で練習後、すぐ合奏するイベントです。2020年1月に初参加し、楽器を演奏する場があれば多くの人が集まり、楽器を続けられることを、身をもって学びました。
(2)吹奏楽部経験者からの要望
2020年からのコロナ禍の影響で様々な活動が制限されました。その時、高校新入生から「吹奏楽部員としてではなく、また楽器を吹きたい」という声や、高校吹奏楽部の卒業生から、「大学のサークルや市民団体が活動を休止しているが、楽器を演奏したい」という声を聞き、新型コロナウイルスや部員数減少で活動に困っていた吹奏楽部も巻き込みイベントを企画しました。
2.具体的な内容
A.楽器演奏イベント開催
少し感染状況が落ち着いた2021年夏休みと2022年春休みに楽器演奏イベントを企画・開催しました。このイベントでは多くの在校生や卒業生も参加し、人数が少なくなっていた吹奏楽部のメンバーも交えて20~30人で演奏をすることができました。2023・2024年夏には会場をホールに移し、それを見て育った卒業生有志が実行委員として夏の演奏イベントを運営するようになりました。
2023年夏開催のイベントでは金管楽器奏者が多く、木管楽器奏者が不足したことから、私の高校時代の同級生に声をかけて客演をお願いしました。そのときの活動に影響され「自分たちの同期でも同じようなことをやりたい」という声が上がり、私は事務局を引き受け「楽器演奏イベント」の元となる活動が始まりました。
B.高校の同期を軸とした合奏イベント
○2023・2024年の活動
早速、高校吹奏楽部の同期に声をかけ、楽器演奏イベントを企画しました。20名弱の同期の中から5名が参加してくれました。2023年の11月には横浜市営の音楽練習室を借り、高校時代に演奏した曲をベースに半日ほど演奏活動を始めました。半数程度のメンバーが高校や大学で演奏して以来でしたが、楽しめたとのコメントが多く集まりました。
イベントが好評でしたので、翌2024年6月に、今度は横浜市の公会堂で演奏イベントを行い、後輩にも声を掛けるなどして参加者は7名と増えました。当日は10時から15時まで練習、15時半から最終合奏というスケジュールで最終合奏は家族など関係者向けに公開し、「ブロックM」「オーディナリーマーチ」などの行進曲を4曲、「オーメンズオブラブ」「Bling-Bang-Bang-Born」「ジャパニーズグラフィティ12」などのポップスを3曲の計7曲を披露しました。演奏参加者からのコメントとしては、ホールでの演奏は良かったという声が多かった一方で「ふだん吹いていないので、1日通しての演奏は疲れる」という声もありました。

2024年11月には再び音楽練習室で開催しました。参加者は6名でしたが、「ジングルベル」「ディープパープルメドレー」、途中であきらめた曲2曲もあわせて、都合8曲を練習しました。活動時間がちょうどいいものの、参加人数が増える中で練習室での活動自体が窮屈となり始め、場所の確保が課題となりました。とはいえ、秋は発表会シーズンでホールも取りにくいため、初夏はホール、秋は練習室というパターンが生まれました。

○2025年
(1)合奏イベントの立案
2025年5月のイベントは前年の反省を踏まえ、横浜市の公会堂で午後半日程度としました。曲目は行進曲として「南風のマーチ」「横浜市歌」「星条旗よ永遠なれ」の3曲、吹奏楽オリジナルを含むアンサンブル曲として「ホルストの第1組曲」「崖の上のポニョ」「海の見える街」の3曲、ポップスとして「ジャパニーズグラフィティ14」など演奏者8名で演奏することとなりました。しかし会場が日中単位(9時~17時)の貸出しのため、「疲れてしまうから半日でよい」という声を反映すると、午前中が空いてしまうための活用法について課題がありました。
C.職場関係者とのイベント開催
午前中の活用方法に悩んでいた2025年3月のことでした。2024年に人事交流で異動した先の職場で楽器を演奏している先輩に「ホール、半日空いてますが、職場で人を誘って演奏活動しますか?」と声をかけてみましたら、「やってみよう」という話になりました。その先輩以外にも勤務先にも「今は演奏を中断しているが機会があれば再開したい…」という方も一定数いらっしゃり、同窓会イベントの半日空いていたホールの午前中を使用し、職場関係者とその友人を核とする合奏イベントを実施することになりました。こちらも8名の参加があり、吹奏楽の代表的マーチ「アルセナール」、T-SQUAREの和泉宏隆曲の「宝島」他「ルパン三世」、「君の瞳に恋してる」などポップスを中心に演奏を行うことができました。

3.課題
(1)楽器
近年はドラムセット(大小様々なドラムとシンバル)が常設の練習室もあることが多くなりましたが、ホールとなるとドラムセットや鉄琴、木琴は最低限主催者側で確保が必要です。またコントラバスやユーフォニウム、ホルン、チューバなどの金管楽器は学校備品を使用している比率が高く「演奏したいが楽器がない」という状況です。楽器レンタルサービスもありますが、受益者負担にしても割高で、団体負担にするにしても不公平感があります。
(2)楽譜
少人数の場合はアンサンブル譜が数千円で購入できますが、フル編成(木管・金管・打楽器など含み多くのパートがある大編成)の楽譜だと一冊最低数万円はします。民音音楽博物館音楽ライブラリも方法の一つではありますが、その都度手続するのは大変です。
(3)会場確保
会場については、近年公営の音楽施設の整備も進んでおり、楽器練習室でよければ半日でも数千円、ホールでも時期を選び、会場の空きを探せばお手頃価格で使用できることは有り難いです。一方で、団体構成員が明確でないと優先予約や抽選に参加できない施設もあり、単発の音楽イベント団体では空き会場を探すしかないところも寂しいところです。
4.成果
同窓会、職場双方ともに10名未満のミニバンドで、メンバーも出入りはありますが固定化しています。なかなか新規参加者が増えない現状の中、双方のイベントに関する興味関心は高く、参加者の中からは楽器編成の面から合同にした方が良いのではないかという提案もありました。本年12月に開催するイベントを実施するに当たり、広報関係においても、各バンドそれぞれに演奏者募集していたことを一体化したことで、7月末までに20名のメンバー申込みを得ることができました。
今回まで合奏イベントの運営に10回以上関わる中で思うことは
①仲間の協力の大切さ
②アンテナを張り、声がけをする
③熱意を持つこと
の三点です。
各集団の中にも「音楽をやりたいが、毎週は無理」や「いきなり知らない所に飛び込むことも不安」という方がきっといるはずです。合奏をしたことのあるメンバーであるからこそ、それぞれ何らかの横のつながりがあり、身近なところから始めることで、参加しやすくなるということも考えられます。楽器を持っている、演奏しているということが共通のつながりであり、自己紹介などの際に「楽器やってました」と発言すると「実は私も…」とつながることも多くあります。また演奏曲に関しては「知らない曲ばかり」だと参加しにくいですが、聴いたことある曲や演奏した曲があると身近に感じ、参加意欲が湧きます。
5.抱負
(1)合同開催
現在は自身が所属する集団の中で、単発の音楽サークルや市民楽団を作って活動しているようなものであり、その数は気づけばその集団は3つほどになっています。当初は「仲間内のイベントなので外部の人はちょっと」という雰囲気でありましたが、それぞれの集団共通の課題である「メンバー不足」や「運営の担い手問題」に向き合うべく「合同開催」など様々な企画を練っているところです。
(2)「ゆるいつながり」を維持する仕組みづくり
演奏活動自体、市民団体のように毎週や毎月同じ日に活動をということができる人ばかりではなく、年1から2回程度の「ゆるいつながり」に価値を感じている参加者も多いです。執筆時点では高校時代の同期を核として、無理なく運営できる仕組みを模索しています。
(3)音楽の灯を絶やさない
現在は「人のつながり」で構成されていますが、どこか落ち着く場所ができれば「地域にある”演奏したい”というニーズ」とも結びつくことができるのではないかとも考えています。コロナ禍終息後、各地で合奏の単発イベントが再開されるようになりました。現在参加者はコロナ禍前よりも増えているように感じており、楽器を演奏したいというニーズは高まっているように感じます。皆様の周りでも、身近なところに声をかけて「音楽の灯火(ともしび)」を絶やさず普及していってほしいと思います。
地域音楽コーディネーターや生涯学習音楽指導員として皆さまの活動を掲載しませんか?
活動紹介やイベント告知をご希望の方は、下記のページをご覧ください
音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。
詳しくは下記をご覧ください。