地域音楽コーディネーター養成講座プログラム
2025年度 養成講座プログラム
講義時間が変更になる場合がございます
2025年度 養成講座
【大阪2月】
2月22日(日)
講義時間が変更になる場合がございます
10:10-11:10
「生涯学習と音楽」
地域音楽コーディネーターの仕事と今日的意義について
講義内容
地域音楽コーディネーターはどのような仕事で、何が期待されているのかをお話します。
講師


久保田 慶一(くぼた けいいち)
日本大学大学院 講師
放送大学 講師
公益財団法人音楽文化創造 理事
東京藝術大学大学院修了。音楽学博士、芸術学修士、カウンセリング修士、経営学修士。東京学芸大学教授、国立音楽大学副学長・教授、東京経済大学客員教授を経て、2025年4月より日本大学大学院、放送大学の各講師。
11:20-12:20
「文化と地域創生」
音楽の力で地域を元気にする
講義内容
国や地方の文化政策についての解説と、東大阪市の文化政策をもとに文化創造館で実施している、市民参加オペラや地域を題材にした創作ミュージカル、子供たちへの事業など、音楽の力で地域を元気にする取り組みについてお話しします。
講師


渡辺 昌明(わたなべ まさあき)
東大阪市文化創造館 館長
全国公立文化施設協会 コーディネーター
東洋大学経済学部卒業、民間企業の営業職を経て財団法人立川市地域文化振興財団に勤務。2014年に事務局長に就任。財団在任中は地域や市民と連携した市民オペラ、演劇祭、などの市民参加型事業や300回を超えるロビーコンサート、市内全20校へのアウトリーチ事業に加え、毎年200名以上の一人親家庭の親子をホール事業に招待するなど、普及事業、社会包摂事業に取り組んできた。2019年9月東大阪市文化創造館開館と同時に初代館長に就任し現在に至る。
13:30-14:30
「地域文化マネージメント」
持続可能な心に残る演奏会を開催しよう!
講義内容
演奏者も来場者も皆が共感出来る時間と空間をつくる秘訣とは?
実践内容を紹介しエピソードを交えてお話しいたします。
講師


安川 裕子(やすかわ ゆうこ)
声楽・合唱指揮
神戸女子短期大学 非常勤講師
全国大学音楽教育学会 会員
“円”女声ハーモニー・女声合唱団「花みずき」 指揮者
大阪音楽大学大学院音楽研究科オペラ研究室修了。天野春美氏師事。オペラ「フィガロの結婚」スザンナ、「コジ・ファン・トゥッテ」デスビーナ、オペレッタ「こうもり」アデーレ、合唱オペラ「いのうもののけ」稲生平太郎、ミュージカル「寝屋のはちかづき」観音様役で出演。関西フィルハーモニー管弦楽団、神戸市室内合奏団との共演の他ソプラノリサイタルをポートピアホテルにて開催。プロ合唱団である神戸市混声合唱団、大阪音楽大学カレッジオペラハウス合唱団所属後、武庫川女子大学附属中学行高等学校コーラス部、合唱団ことのは、関西学院大学混声合唱団エゴラドのヴォイストレーナーを務める。“円”女声ハーモニーを2003年より指揮し2015年全日本お母さんコーラス全国大会に出演。また同年より大阪成蹊女子高校コーラス部の指揮を始め全日本合唱コンクール大阪府大会金賞を受賞し関西大会に出演。大阪成蹊学園コーラス部短大・大学コーラス部の指揮では全日本合唱コンクール関西大会金賞、アンサンブルコンテスト大阪大会金賞を受賞。その他合唱指揮にて受賞歴多数。指揮法を斉田好男氏に師事。現在神戸女子短期大学非常勤講師・全国大学音楽教育学会会員・“円”女声ハーモニー・女声合唱団「花みずき」指揮者。
14:40-16:40
「音楽企画書の書き方」
ターゲットを明確にして、キャッチフレーズを考えれば、
企画は自ずと出来上がる!
講義内容
ターゲットを明確にし、キャッチフレーズを考えれば、企画は自ずと出来上がる。さぁ、一緒に考えましょう!
講師


大谷 邦郎(おおたに くにお)
グッドニュース情報発信塾 塾長
1984年、株式会社毎日放送入社。40歳代半ばまでは大半を「記者」として過ごし、テレビでは経済番組のプロデューサーとして活躍。ラジオ時代には放送業界では最高峰の賞「ギャラクシー賞大賞」や「民間放送連盟賞最優秀賞」などを受賞、その後、ラジオ報道部長、宣伝部長などを歴任。取材する側、取材される側をともに経験したことにより、情報発信に関する独自のノウハウを蓄積。2016年に毎日放送を早期退社し、グッドニュース情報発信塾を立ち上げ、現在に至る。情報発信の各種セミナーの講師やコンサルタントとして活躍中。また講談作家、追手門学院大学「笑学」研究所客員研究委員の肩書きも持つ。
2025年度 養成講座
【オンライン7月】
7月6日(日)
終了しました
10:10-11:10
「生涯学習と音楽」
地域音楽コーディネーターの仕事と今日的意義について
講義内容
地域音楽コーディネーターはどのような仕事で、何が期待されているのかをお話します。
講師


久保田 慶一(くぼた けいいち)
日本大学大学院 講師
放送大学 講師
公益財団法人音楽文化創造 理事
東京藝術大学大学院修了。音楽学博士、芸術学修士、カウンセリング修士、経営学修士。東京学芸大学教授、国立音楽大学副学長・教授、東京経済大学客員教授を経て、2025年4月より日本大学大学院、放送大学の各講師。
11:20-12:20
「文化と地域創生」
地域音楽コーディネーターが各拠点をつなぐ役割を担う
講義内容
多様な人々の多様な背景を繋ぎ,ファシリテーター・ステークホルダーとして担っていく役割を一緒に考えていきましょう。
講師


渡辺 行野(わたなべ ゆきの)
文京学院大学人間学部児童発達学科・同大学院人間学研究科 准教授
ふじみ野市文化協会 理事
文化振興審議会 委員
学校運営協議会 委員
小・中・高校にて教育実績を持ち、現在は保育・幼稚園・小学校の保育者・教員養成に注力している。
【著書】 『教育音楽』:「連載 教えてゆきの先生!生徒の心ときめく鑑賞授業」(音楽之友社) 『音楽指導DVD出演・指導・解説・製作』:「音楽を愛する子どもを育てる手立て~身体と声を結び付け歌唱表現につなげる指導実践~」(JLC:ジャパンライム株式会社)
他
13:30-14:30
「地域文化マネージメント」
文化で地域をつなぐ・・・
街の先生と学校と、地域をつなぐノウハウ教えます!!
講義内容
文化という言葉は、オールマイティのカード。地域をつなぐ糸口の見つけ方、地域のキーマンとの交渉方法、資金集めなど、実践してきたことを紹介し、受講生の皆様からの質問に答えていきたいと思います。
講師


中村 牧(なかむら まき)
公益財団法人音楽文化創造 理事
3才からピアノを始め、音楽に親しみ続ける。横浜国立大学教育学部音楽専攻卒業、日本クラシック音楽マネジメント協会(現:一般社団法人日本クラシック音楽事業協会)の社団化・立ち上げに従事し、クラシック音楽業界でのネットワークを生かし、横浜みなとみらいホールや指定管理施設第1号となった杉田劇場の立ち上げに携わり、2006年同劇場館長。横浜みなとみらいホール総支配人を経て2014年4月より現職。日常に文化があるが信条。地域文化の拠点として、「地域と一緒にできること」をモットーに、異世代交流のワークショップ(杉劇リコーダーず、杉劇☆歌劇団)、障がいのあるなしに関わらず参加できるワークショップ(杉劇にこにこ合唱団)やアウトリーチ、区民参加型事業、区民ボランティア組織(杉劇@助っ人隊)による事業、地域の伝承事業、地域文化の担い手育成事業、などを手掛ける。さらに、学校運営協議会や磯子区制100周年実行委員会、地域ケア会議などに参画し、文化でつなぐ地域づくり、街づくりに貢献。今年度からは、一歩進んで、学校や音楽団体をつなげて地域文化クラブの杉田劇場モデルを確立できたこと、NPO法人による劇場運営を支援し推進し、ますます地域と文化、音楽と人と、結ぶことを楽しんでいる。
14:40-16:40
「音楽企画書の書き方」
ターゲットを明確にして、キャッチフレーズを考えれば、
企画は自ずと出来上がる!
講義内容
ターゲットを明確にし、キャッチフレーズを考えれば、企画は自ずと出来上がる。さぁ、一緒に考えましょう!
講師


大谷 邦郎(おおたに くにお)
グッドニュース情報発信塾 塾長
1984年、株式会社毎日放送入社。40歳代半ばまでは大半を「記者」として過ごし、テレビでは経済番組のプロデューサーとして活躍。ラジオ時代には放送業界では最高峰の賞「ギャラクシー賞大賞」や「民間放送連盟賞最優秀賞」などを受賞、その後、ラジオ報道部長、宣伝部長などを歴任。取材する側、取材される側をともに経験したことにより、情報発信に関する独自のノウハウを蓄積。2016年に毎日放送を早期退社し、グッドニュース情報発信塾を立ち上げ、現在に至る。情報発信の各種セミナーの講師やコンサルタントとして活躍中。また講談作家、追手門学院大学「笑学」研究所客員研究委員の肩書きも持つ。
2025年度 養成講座
【名古屋11月】
11月23日(日)
終了しました
10:10-11:10
「生涯学習と音楽」
地域音楽コーディネーターの仕事と今日的意義について
講義内容
地域音楽コーディネーターはどのような仕事で、何が期待されているのかをお話します。
講師


久保田 慶一(くぼた けいいち)
日本大学大学院 講師
放送大学 講師
公益財団法人音楽文化創造 理事
東京藝術大学大学院修了。音楽学博士、芸術学修士、カウンセリング修士、経営学修士。東京学芸大学教授、国立音楽大学副学長・教授、東京経済大学客員教授を経て、2025年4月より日本大学大学院、放送大学の各講師。
11:20-12:20
「文化と地域創生」
文化を活かしたまちづくり
講義内容
これからの時代に必要な「文化をまちづくりに活かす」視点や「市民の力をまちづくりに活かす」視点について考えます。
講師


広中 省子(ひろなか しょうこ)
ジョイントフェスティバル協議会 会長
1957年愛知県生まれ。38年前3人の子どもを育てる中で、「地域に子育てと文化でつながる仲間を広げ、舞台芸術をとおして子どもも大人も人間性豊かに育ち合う」ことを目的とする「おやこ劇場」に出会う。以来、日進おやこ劇場運営委員長、子ども・おやこ劇場東海連絡会運営委員長、子どもと文化全国フォーラム理事などを歴任し、子どもや地域の文化活動に深くかかわってきた。2018年、市民公募で長久手市文化の家館長に就任、退職後2022年4月より現職。公立文化施設と芸術団体、市民団体の三者が連携協働し、子どもたちと舞台芸術との出会いを創出する「ジョイントフェスティバル協議会」で、子どもたちが豊かな文化環境の中で育つことを目指している。
13:30-14:30
「地域文化マネージメント」
社会貢献活動 ―地域や行政とのつながりー
講義内容
音楽を通じた社会貢献活動を行う上で、より大きな成果に繋げる効果的な方法のひとつとしてNPO法人化がある。
音楽事業を事例として、社会貢献(NPO法人の役割)やNPO法人格所得後のメリットなど、地域や行政とのつながりを交えて、お話しします。
講師


藤根 由紀子(ふじね ゆきこ)
NPO法人みらいっこ 理事長
知多半島春の国際音楽祭 大府市実行委員長
保育園設立 管理責任者
音楽アウトリーチ事業活動 事務局長
市内保育園演奏会
子育て支援イベント企画
KAZOCLA実行委員会(家族でクラシック)
地域音楽コーディネーター
1990年-2014年ヤマハ音楽教室システム講師を23年。結婚して子どもが出来たことで子育て支援事業に興味を持ち、2008年NPO法人を設立。市内で2つの施設の指定管理を行う。その他にエンターテインメント事業として、主にドイツ、ウイーン、チェコなどの海外からクラシックやジャズのアーティストたちを招き、愛知県内を中心にイベントやコンサートを開催。優しい旦那さまと、2人の子どもに恵まれた普通のお母さんです。
14:40-16:40
「音楽企画書の書き方」
音楽企画書をつくる ―その意味と活用―
講義内容
さまざまな人をつなぐコーディネーターにとって欠かせない企画書。どのようにつくり活用するか、グループワークをとおして紐解いていきます。
講師


生田 創(いくた そう)
長久手市文化の家 前館長
名古屋生まれ、瀬戸市在住。1995年に㈱三光に入社。主に舞台音響を務める。1999年より長久手市文化の家にて企画制作の担当。これまでに長久手国際オペラ声楽コンクール、音楽フェスティバル「おんぱく」、アウトリーチ事業「であーと」など、数多く手掛ける。2021年より、東京大学先端科学技術研究センターと連携し、自然とアート(感性)の関係性を研究し社会実装を目指す「Nagakute Nature-Centered Project(NNCP)」を推進中。愛知県立芸術大学、名古屋芸術大学、名古屋大学、南山大学、中部楽器技術専門学校、ステージラボ(一般財団法人地域創造主催)などで講師を務める。日本アートマネジメント学会、日本音楽芸術マネジメント学会、各会員。2023~2025年9月まで長久手市文化の家館長。
2025年度 養成講座
【オンライン1月】
1月18日(日)
終了しました
10:10-11:10
「生涯学習と音楽」
人とのつながりの中で音楽を学ぶことの意味とその支援について
講義内容
人とのつながりの中で音楽を学ぶことについて、その教育的な意義と支援法についてお話します。
講師


志々田 まなみ(ししだ まなみ)
文部科学省国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 総括研究官
公益財団法人音楽文化創造 理事
愛知県豊橋市生まれ。教育学(社会教育・生涯学習)が専門。特技:広島弁。研究のテーマは、学校・家庭・地域の連携・協働。広島経済大学教授を経て、2017年から文部科学省国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官。
11:20-12:20
「文化と地域創生」
文化を活かしたまちづくり
講義内容
これからの時代に必要な「文化をまちづくりに活かす」視点や「市民の力をまちづくりに活かす」視点について考えます。
講師


広中 省子(ひろなか しょうこ)
ジョイントフェスティバル協議会 会長
1957年愛知県生まれ。38年前3人の子どもを育てる中で、「地域に子育てと文化でつながる仲間を広げ、舞台芸術をとおして子どもも大人も人間性豊かに育ち合う」ことを目的とする「おやこ劇場」に出会う。以来、日進おやこ劇場運営委員長、子ども・おやこ劇場東海連絡会運営委員長、子どもと文化全国フォーラム理事などを歴任し、子どもや地域の文化活動に深くかかわってきた。2018年、市民公募で長久手市文化の家館長に就任、退職後2022年4月より現職。公立文化施設と芸術団体、市民団体の三者が連携協働し、子どもたちと舞台芸術との出会いを創出する「ジョイントフェスティバル協議会」で、子どもたちが豊かな文化環境の中で育つことを目指している。
13:30-14:30
「地域文化マネージメント」
地域連携と音楽活動
誰もが自由で、創造性を発揮できる共生社会の実現を目指して
講義内容
行政や公共施設と連携し、個人、企業、団体からの寄付、協力で実施する地域に開かれた音楽活動とは
講師
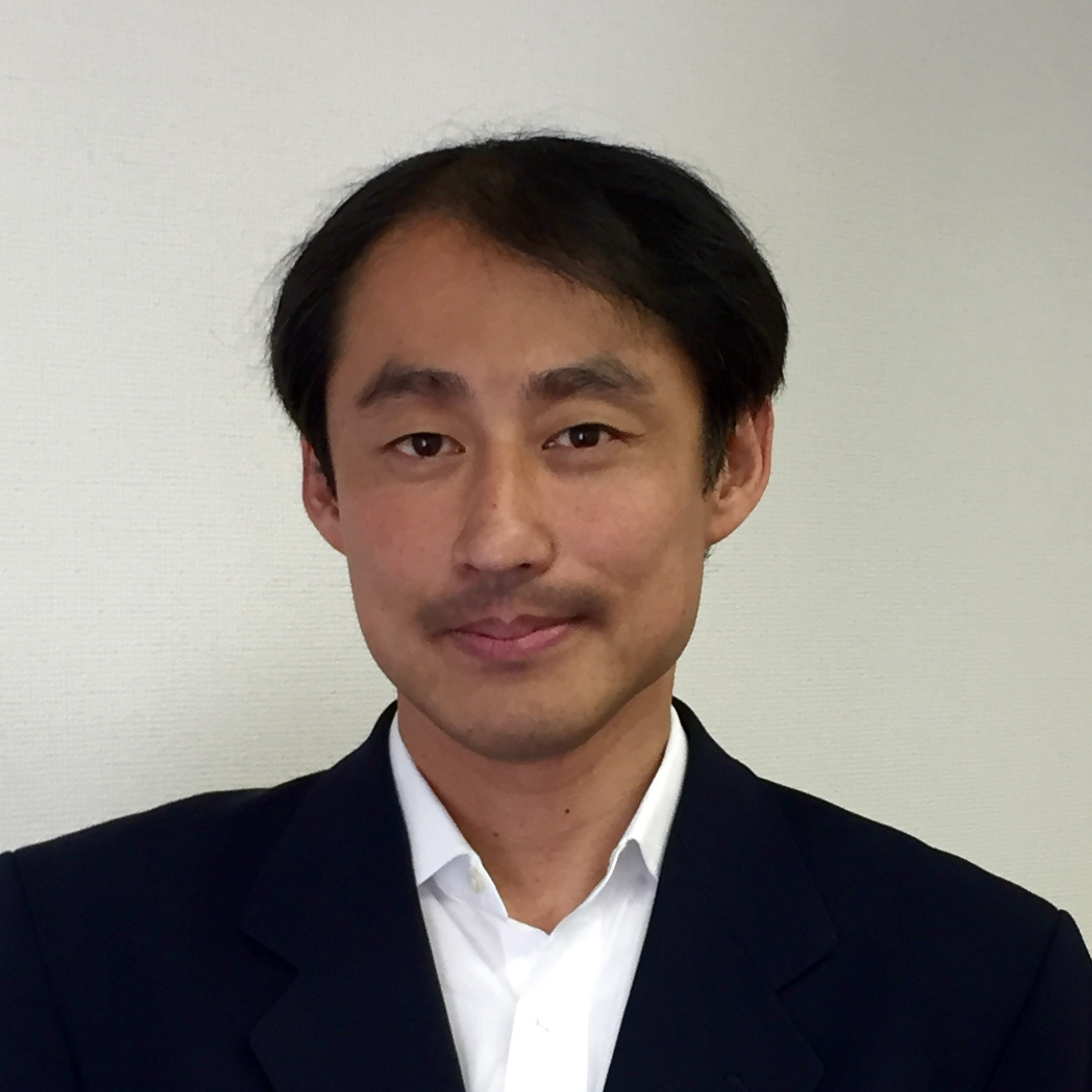
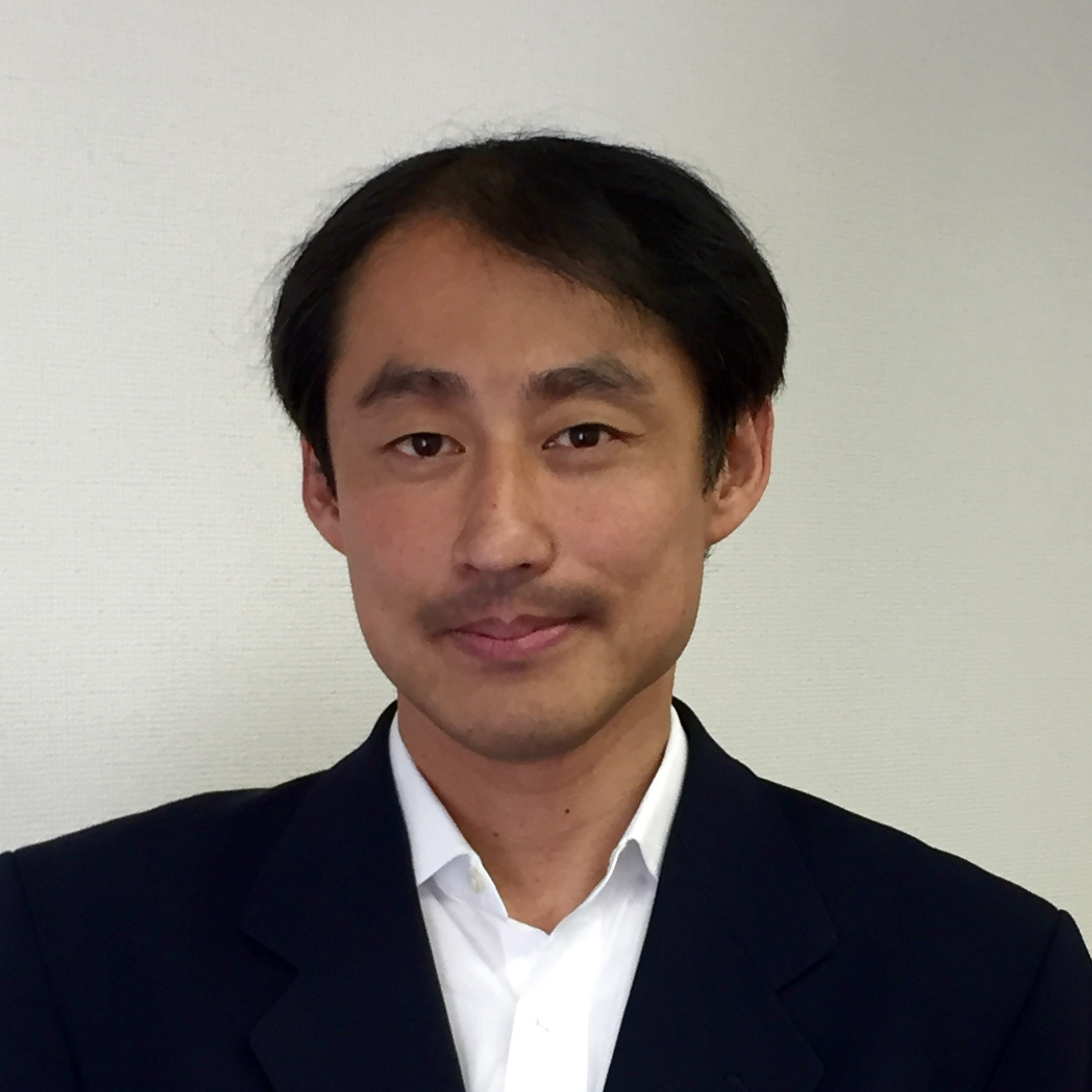
菊川 穣(きくがわ ゆたか)
一般社団法人エル・システマジャパン 代表理事
公益財団法人音楽文化創造 理事
1971年神戸生まれ。2~5歳をフィンランドで過ごす。1995年ロンドン大学ユニバーシティーカレッジ地理学部卒業。1996年同大学教育研究所政策研究修士課程修了(M.A)帰国後、社会工学研究所を経て、1998年より国連教育科学文化機関(ユネスコ)南アフリカ事務所勤務。2000年より国連児童基金(ユニセフ)レソト、エリトリア事務所勤務。2007年財団法人日本ユニセフ協会へ移り、J8サミットプロジェクトコーディネーター、団体・組織事業部を経て、2011年3月より東日本大震災緊急支援本部チーフコーディネーター。2012年3月、一般社団法人エル・システマジャパンを設立し以降現職。
14:40-16:40
「音楽企画書の書き方」
音楽企画書をつくる ―その意味と活用―
講義内容
さまざまな人をつなぐコーディネーターにとって欠かせない企画書。どのようにつくり活用するか、グループワークをとおして紐解いていきます。
講師


生田 創(いくた そう)
しらかわホール チーフ・プロデューサー
名古屋生まれ、瀬戸市在住。1995年に㈱三光に入社。主に舞台音響を務める。1999年より愛知県長久手市文化の家にて企画制作の担当。これまでに長久手国際オペラ声楽コンクール、音楽フェスティバル「おんぱく」、アウトリーチ事業「であーと」など、数多く手掛ける。2021年より、東京大学先端科学技術研究センターと連携し、自然とアート(感性)の関係性を研究し社会実装を目指す「Nagakute Nature-Centered Project(NNCP)」を推進中。愛知県立芸術大学、名古屋芸術大学、名古屋大学、南山大学、中部楽器技術専門学校、ステージラボ(一般財団法人地域創造主催)などで講師を務める。日本アートマネジメント学会、日本音楽芸術マネジメント学会、各会員。2023~2025年9月まで長久手市文化の家館長。2025年11月より、しらかわホール(愛知県名古屋市) チーフ・プロデューサーに就任。











