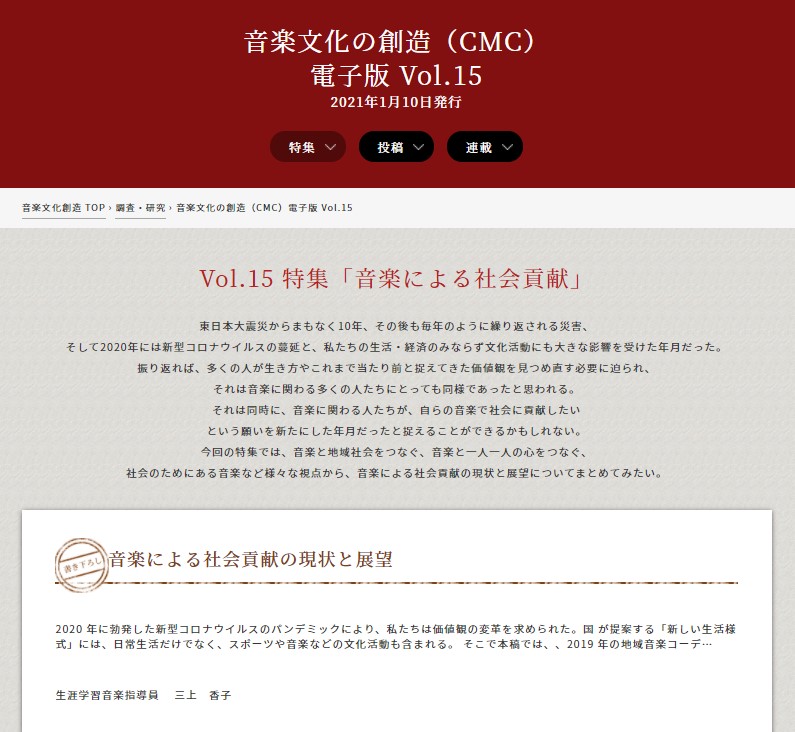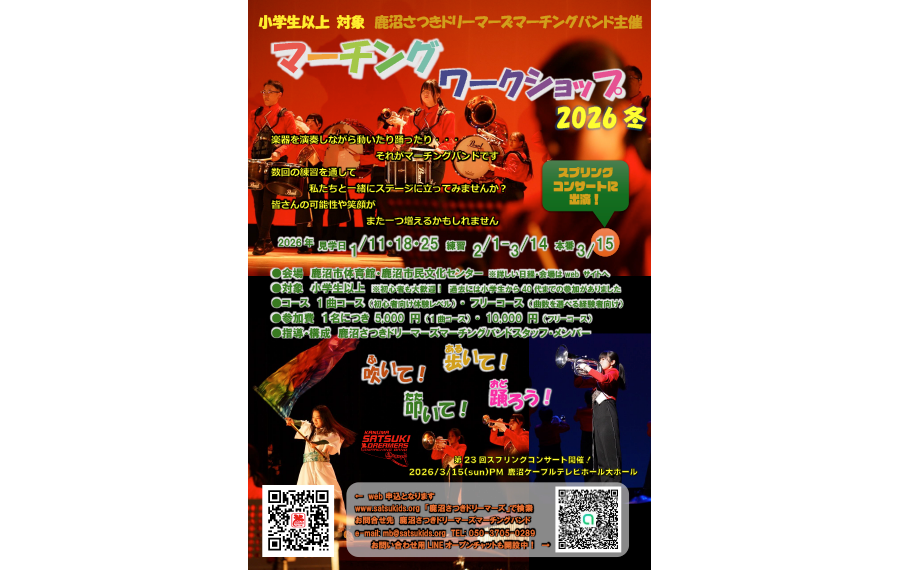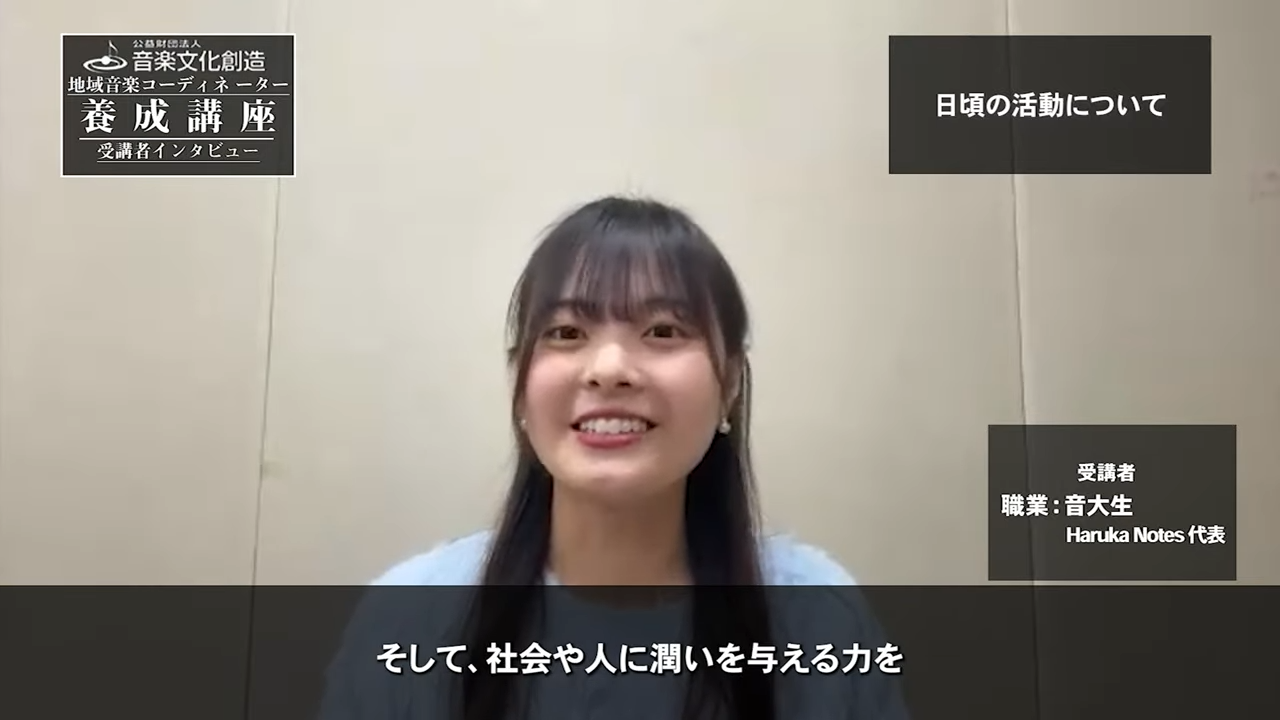2020年は誰しもが未曾有のパンデミックに翻弄されました。この未知のウィルスの蔓延により年を越した今なお先の見通しは立っていません。そんな中、芸術活動は不要不急か? という問いに多くの人が否応なしに直面しています。音楽文化と生涯音楽学習の総合情報・研究誌「音楽文化の創造」(CMC=Creating Music Culture)Vol.15の特集は「音楽による社会貢献」です。音楽や芸術活動がどのように社会に貢献できるのか。現状と展望が4本の書き下ろしにまとめられ、幾つもの示唆を与えてくれます。他に連載、2本の投稿論文で成る今号は読みごたえのある力作が満載です。ここでその概要をご紹介します。ぜひ、本文をお読みください。
(「音楽による社会貢献の現状と展望」 生涯学習音楽指導員 三上 香子)
(「ヤマハが取り組む音楽を通じた街づくり(おとまち)」(株)ヤマハミュージックジャパン 事業企画部事業開発課 主任 細田 幸子)
公益法人としてオンリーワンの活動とは何か、と模索する中、設立10周年目には明確に「人と人のつながる場を創り社会に貢献したい」という方向性を見定めています。横浜市との共催事業である「ごちゃまぜ音楽祭」はジャンル、世代、ハンディキャップなど様々な意味合いでごちゃまぜ。違う分野が混ざり合い、時に考え方の変革を促されます。違う視点から新しい活動が育まれることの豊かさが感じられ、たいへん参考になります。
(「音楽を通して『真のごちゃまぜな社会を創る』という大きな目標」 認定NPO 法人アークシップ理事 西 亨)
(「我、COVID-19 の陰の谷を歩むとも -コロナ時代の音楽家と社会貢献」 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科講師 箕口 一美)
(連載:「音楽とキャリア -人生100年時代に向けて-」 第8回:現代の音楽家に必要な教養とは何か 音楽学者 久保田 慶一)
(「早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程2年」 平原 幸輝)
(「オンラインによる大学生へのピアノ指導の在り方 ―紙鍵盤とYouTube を活用して―」 関西福祉大学 木原 加代子)
「音楽文化の創造」(CMC電子版) Vol.15 特集「音楽による社会貢献」を読めば、意欲が湧き、音楽の魅力、可能性を再発見することでしょう。音楽でしかでき得ないことに想いを馳せるきっかけになるかもしれません。ぜひ多くの方にお読みいただきたいと切に思います。
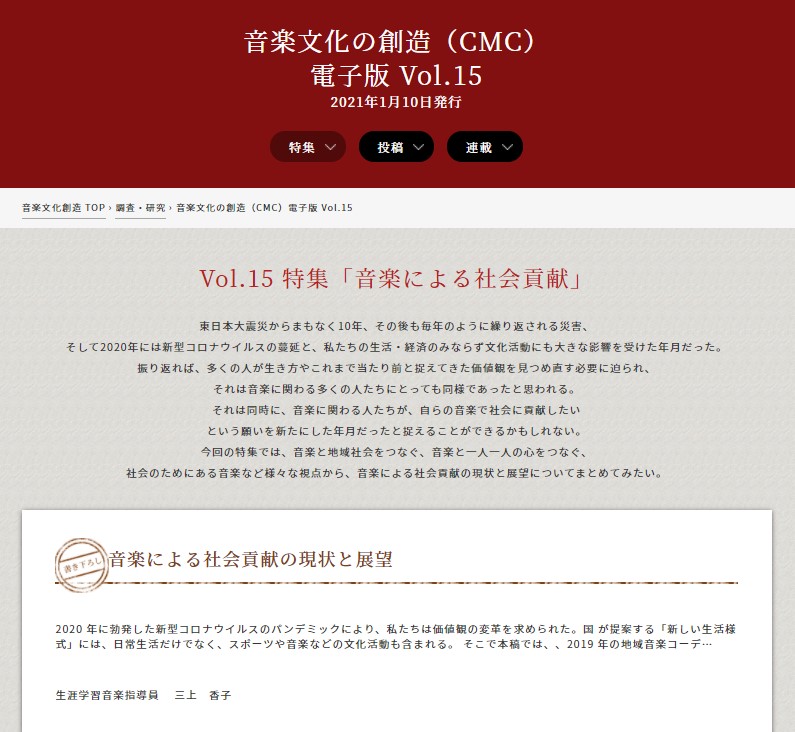
【音楽による社会貢献の現状と展望 NPO法人「音の風」の活動紹介】
NPO法人とは何か? から始まり、設立によるメリット、事業内容など細部まで分類、整理して, ていねいにまとめられています。NPO法人について詳しく知りたい方には役立つこと間違いなしです。このNPO法人の事業が、参加者の生きがいの創出、居場所づくり、人材の育成、つまりは社会貢献に確かにつながっていることに深くうなずくことができます。(「音楽による社会貢献の現状と展望」 生涯学習音楽指導員 三上 香子)
【ヤマハが取り組む音楽を通じた街づくり(おとまち)】
地域コミュニティづくりの観点から具体的な2つの事例(ドラムサークルファシリテーター育成講座、市民参加型音楽祭)が紹介されています。産・官・民が時に協働し、音楽を通じたプロジェクトを実施することで、街が抱える課題の改善に確実に貢献していることが読みとれます。やはり音楽は世代や性別などの垣根を軽々と飛び越え、「楽しく」人々がつながれる魅力にあふれているのです。(「ヤマハが取り組む音楽を通じた街づくり(おとまち)」(株)ヤマハミュージックジャパン 事業企画部事業開発課 主任 細田 幸子)
【音楽を通して「真のごちゃまぜな社会を創る」という大きな目標】
設立18周年のNPO法人の進化の過程がエッセイ風に語られています。公益法人としてオンリーワンの活動とは何か、と模索する中、設立10周年目には明確に「人と人のつながる場を創り社会に貢献したい」という方向性を見定めています。横浜市との共催事業である「ごちゃまぜ音楽祭」はジャンル、世代、ハンディキャップなど様々な意味合いでごちゃまぜ。違う分野が混ざり合い、時に考え方の変革を促されます。違う視点から新しい活動が育まれることの豊かさが感じられ、たいへん参考になります。
(「音楽を通して『真のごちゃまぜな社会を創る』という大きな目標」 認定NPO 法人アークシップ理事 西 亨)
【我、COVID-19の陰の谷を歩むとも―コロナ時代の音楽家と社会貢献】
あるアンケートでは71%が芸術家を non‐essential(「不要不急」)と認定したそうです。芸術活動に携わる人には、いささかショッキングな数字ではないでしょうか。しかし「コロナ禍で最も必要性が低い職業」と言われても仕方ないと思ってしまうのもまた事実です。このような状況下、いかに音楽家が社会的に存在を示し、社会貢献して行くべきか論じています。正にタイムリーな記事です。何より肝要なのは、相手が何を望んでいるか想像すること。具体的な方策を練り、行動に移すこと。オンライン配信の有効性ついても言及されています。(「我、COVID-19 の陰の谷を歩むとも -コロナ時代の音楽家と社会貢献」 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科講師 箕口 一美)
【連載「音楽とキャリア ―人生100年時代に向けて―」第8回現代の音楽家に必要な教養とは】
大学でどんな教養教育(一般教養)を学んだでしょうか。本稿では、まず古代ギリシャ、ローマ時代に始まる教養教育やリベラルアーツの意味をたどります。続いて日本の大学、音楽大学における教養教育の変遷についても述べられています。今求められる「音楽キャリア教育」の重要性についても説かれ、学びなおしに興味がある方には大いに参考になるでしょう。(連載:「音楽とキャリア -人生100年時代に向けて-」 第8回:現代の音楽家に必要な教養とは何か 音楽学者 久保田 慶一)
*投稿論文
【音楽活動を通じたソーシャル・キャピタルの意義―社会学から見た生涯音楽学習の重要性―】
ソーシャル・キャピタルと言う概念が説かれ、音楽活動と健康との密接な関係を統計的分析に基づき明らかにしています。生涯音楽学習の意義と理想的な姿が明確に打ち出されています。(「早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程2年」 平原 幸輝)
【オンラインによる大学生へのピアノ指導の在り方―紙鍵盤とYouTubeを活用して―】
ピアノ指導者のみならずピアノが得意でない人にも有用性が高い記事。オンラインでも技能は高まり、意義あることが納得できます。対面レッスンに活用できるヒントも多く、とても参考になります。(「オンラインによる大学生へのピアノ指導の在り方 ―紙鍵盤とYouTube を活用して―」 関西福祉大学 木原 加代子)
「音楽文化の創造」(CMC電子版) Vol.15 特集「音楽による社会貢献」を読めば、意欲が湧き、音楽の魅力、可能性を再発見することでしょう。音楽でしかでき得ないことに想いを馳せるきっかけになるかもしれません。ぜひ多くの方にお読みいただきたいと切に思います。