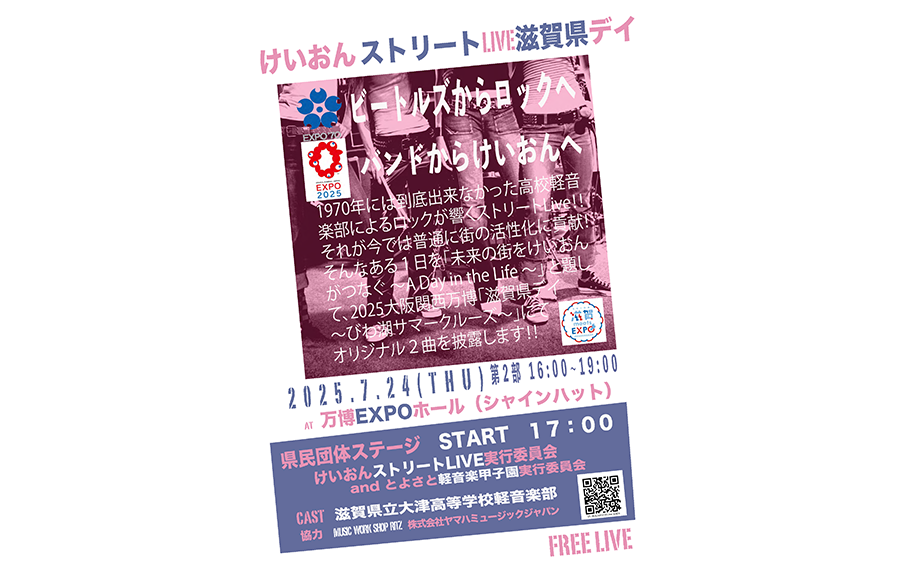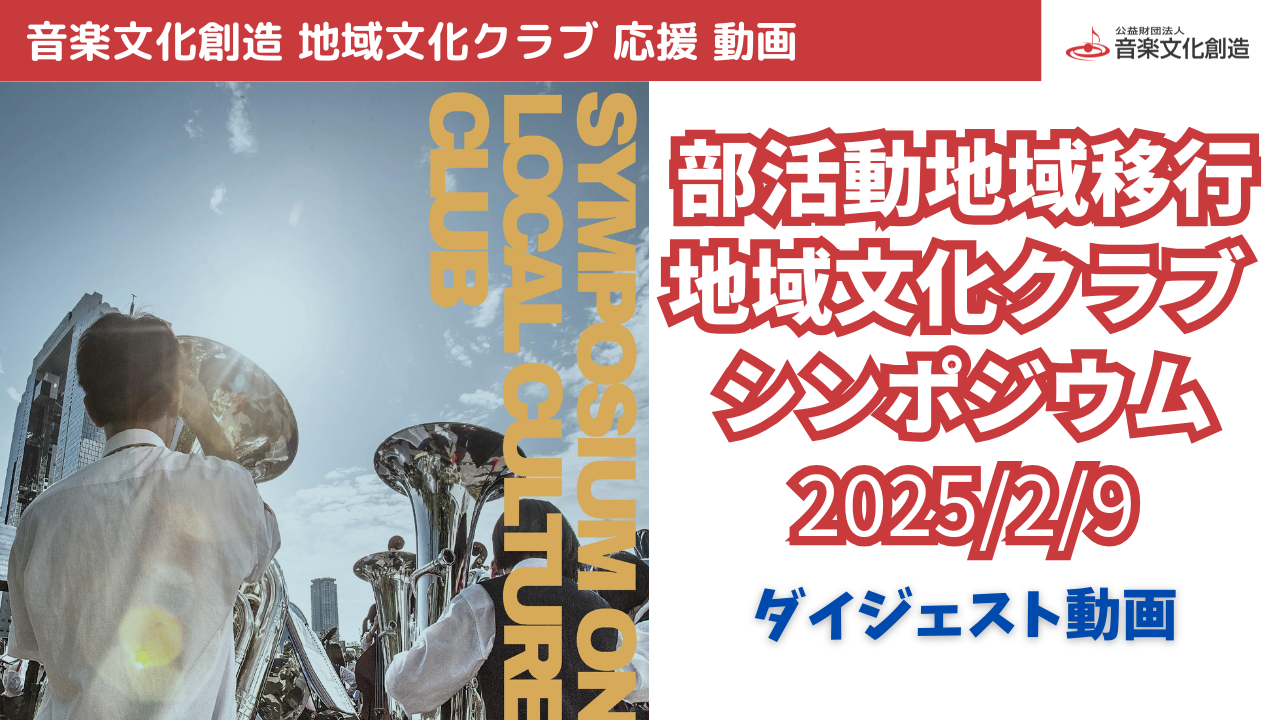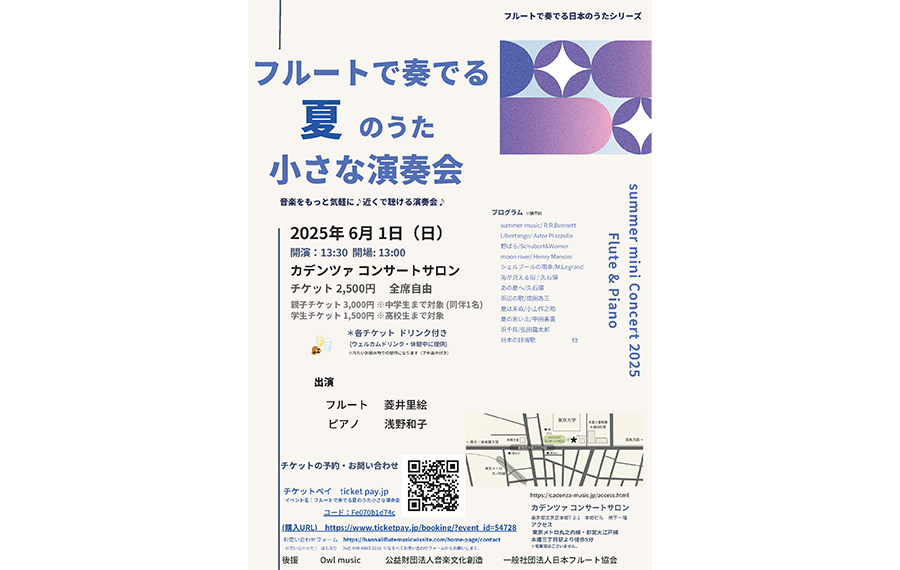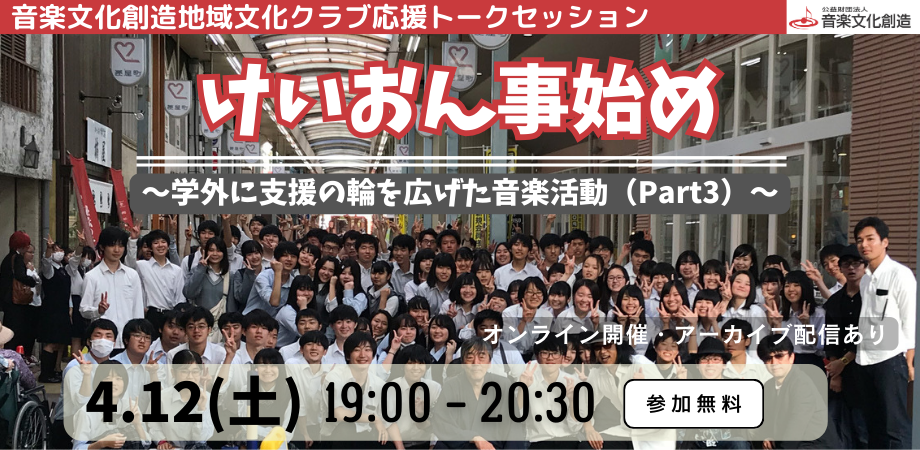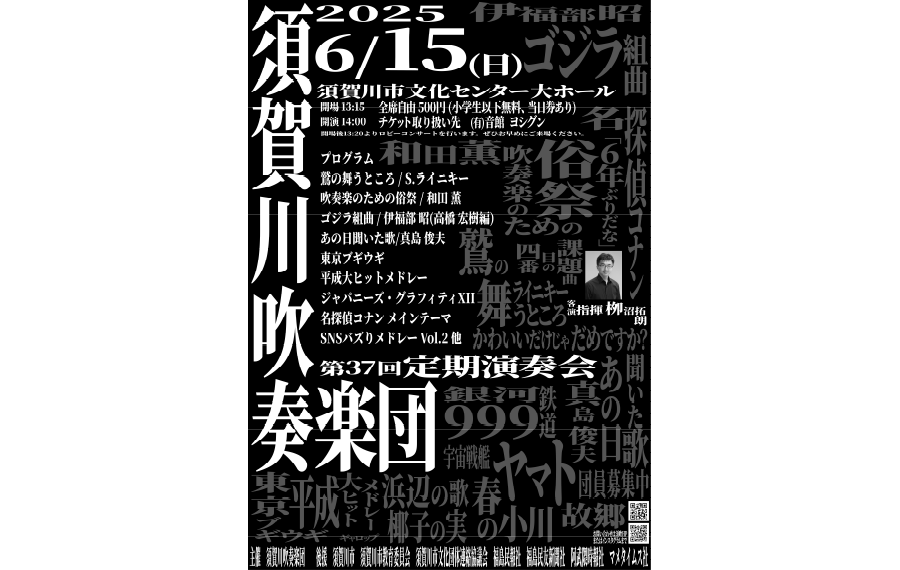記事.png)
<新しい方角(邦楽:日本の伝統音楽)>
箏・三絃演奏家埼玉県 田辺明さん

■活動タイトル:和楽器で埼玉愛
目次■活動開始年:2004年~現在
■場所:関東近郊ホール、イベント、学校アウトリーチ、作曲・編曲、邦楽楽理指導、合奏指導
■対象:小学生~大人
■活動内容
Ⅰ.箏・三味線を始めたきっかけからプロになるまで
(1)和楽器サークル入部
「音」と言えば、工場に響くエンジン音くらいしか聞いてこなかったバイク屋の息子は、学校では10段階すべての成績をまんべんなく取るべく「音楽(芸術)は生きていく上で必須ではない」と10段階で国語は10、音楽は1といった成績を取ったり、高校受験シーズンには「みんなが一斉に勉強し始めたから」という理由から学校では、ただ1人二次募集で受験する等の天邪鬼でした。ジャニーズや小室哲哉全盛の時代にCDを一枚も持ったこともなければカラオケにも行ったことはありませんでした。もちろん伝統音楽にも触れたこともありませんでしたが、大学入学時には「絶対に一風変わったサークルに入ろう」と目論んでいました。その候補に挙がったのが和楽器のサークルでした。「芸術」という概念をほぼ捨て去っていた自分にとって和楽器は「変わったこと」、音楽というより「芸能」といった印象しかありませんでした。
和楽器を始めた頃は、人があまりやっていない稀有なことをやっている、という満足感が強く、またそれまでの趣味といえば、将棋やゲーム(殊に信長の野望や三国志といった戦略系ゲーム)といったやや孤独なものが多かったのですが、NHK将棋トーナメントのオープニングや特定のゲームの曲を和楽器で弾けないものかと考えていました。
始めて少し経ってからでしょうか、お稽古の時に半拍の休符が取れなくて、「あ、これは自分の嫌いな音楽だ」と気づいたのは。しかし同時に定期演奏会等を通じて仲間と合奏したり、共同で演奏会を作り上げていくことの楽しさを感じていました。
大学生時代までは歌うことが一番嫌いでしたが、地歌・箏曲によって自然と歌うことに抵抗はなくなっていました。関東学生三曲連盟という和楽器のサークルの連盟に加入していたこともあり、他大学の仲間と古典曲を合奏する事も楽しみのひとつでした。「そっちの大学の流儀だとそうなるんだね」とか同じ曲でもその違いに興味もありました。
(2)ファミ箏リーダー沖政氏との出会い
そして大学3年生の時に知り合いに頼まれた小学校の箏体験授業で一つの疑問が湧きました。「日本人なのに日本の楽器を全然教えられない、そもそもなぜ珍しいものだと皆思っているんだ…?」と。3年生後半になると就職活動の時期になります。就職氷河期も手伝ってまた天邪鬼は騒ぎ始め、皆必死で就職活動をしている最中、演奏家になりたいという気持ちが強くなっていました。大学4年生のときだったかと思います。とある大きな演奏会の楽器運びのお手伝いに行ったとき、他大学でしたが同学年で同じく手伝いをしていた仲間と「和楽器でゲーム音楽やりたいよね」という会話をしたのが後のファミ箏リーダー沖政一志氏でした。
(3)プロを目指して
大学を卒業後、プロを目指すべく師匠と相談した結果まずは准師範取得を目指しました。師匠の所属する正派邦楽会は演奏の他、邦楽楽理や箏曲史の課題が課せられます。そこで楽典の基礎や邦楽理論を学び(また師匠がその分野に長けていた)、首席で登第することができました。将棋や戦略系歴史ゲームをやっていたせいか、この種の課題には何の抵抗もありませんでしたが、結果が出てから自分はこの分野が武器になるのではないか、と意識し始めます。そして2012年1月第五回牧野由多可賞作曲コンクールにて《箏・三絃二重奏曲 阿修羅》が佳作を受賞してから活動が本格化していったように思います。
(4)沖政氏との再会
そしてその矢先、「ファミ箏第一回演奏会」(2012年4月6日)が開催されることを知り、10年越しに沖政氏と再会します。そこで「次からは演奏と編曲の面で一緒に手伝ってほしい」とのことで以降ファミ箏に参加することになりました。和楽器で色んな曲を弾きたいけど楽譜がないと思っていた20年前と比べると、現在は色んな楽譜や演奏動画もありますが、それを作るための知識やテクニックを学びたいという要望が増えているように思います。現在では正派音楽院にて邦楽理論を教授したり、和楽器による編曲テクニックを学びたいというイベントで講師を務めたりもしています。
今回はその様な活動をしていく中で地元埼玉県出身在住の奏者と知り合い結成した、和楽器で埼玉愛を奏でる和楽器カルテット「サイタマティック」での活動をご紹介いたします。
Ⅱ.和楽器カルテット「サイタマティック」
1.結成にあたって
2015年「和楽器で埼玉愛」を合言葉に、埼玉県出身・在住の演奏家4人(箏&17絃、25絃箏、尺八、三味線)による和楽器カルテットを結成し今年で8年目になります。普段は個々に活動している演奏家ですが、地元で開催されるイベントに地元の奏者で組んで出演しているうちに、自然と違う楽器のメンバーが集まり、グループ名も和楽器カルテット「サイタマティック」と自然に決まりました。地元ならではのトークや楽曲が受け入れられているのだと思います。ちょうど自虐的な県民性や埼玉ポーズ、映画「翔んで埼玉」のヒット時期と重なったのも大きいと思います。大宮で開催された世界盆栽大会記念事業や小江戸川越の伝統和芸鑑賞会、埼玉WABISABI大祭典といった各種イベントやホール主催のコンサート、学校アウトリーチ、POPSやゲーム音楽のカバーの他、伝統・文化・名産等をモチーフとした楽曲を中心として地域に根ざした活動を展開しています。




2.目指している音楽
基本コンセプトは「埼玉」です。埼玉県内の市をテーマに《盆栽の街(大宮区盆栽町)》《うなぎ(さいたま市浦和区、川越市他)》《白銀の霧(秩父市三峯神社)》等のオリジナル曲を作っています。また渋沢栄一の出身地が深谷市なので、2021年のNHK大河ドラマ《青天を衝け》のテーマ曲や、THE ALFEEの高見沢俊彦さんが埼玉県蕨市出身ということで《星空のディスタンス》、海なし県民の海を見たいという思いをのせて古典の名曲《春の海》等も加えます。「音楽」という観点からジャンルはバラバラですが「埼玉」という観点からは共通です。●和楽器で埼玉愛を奏でるカルテット「サイタマティック」
https://shopper.chiicomi.com/66981/
●サイタマティック ホームページ
https://saitamatic.wixsite.com/website
Ⅲ.具体的な活動
1.活動にあたって
現在は月に1、2回定期的なミーティング(WEB・対面)を設定し、渉外・コンサート・WEB・会計とメンバーが担当し進捗・報告を行っています。リハーサルで集まった時に決める議案、WEB会議で決める議案等を本番から逆算し、常に1、2回先のミーティングを設定しています。曲目やスケジュール、演奏する地域の名産を共有するのも重要な事案です。

2.訪問コンサート
(1)小学校
- 2019年 さいたま市立与野南小学校、谷田小学校
- 2020年 さいたま市立城南小学校、常盤小学校
- 2021年 さいたま市立美園北小学校


(2)高齢者施設
- 2022年 センチュリーシティ大宮公園
(3)イベント
- 2021年11月 埼玉WABISABI大祭典2021
●埼玉WABISABI大祭典2021アーカイブ
2022年3月 さいたま市民会館おおみやありがとうコンサート さいたま市大宮区で52年間利用されてきたさいたま市民会館おおみや閉館記念事業のコンサート。《うなぎ》《鉄道の街》《鎌倉殿の13人メインテーマ》等を演奏しました。お客さまも地元の方が多く、埼玉トークでいつも盛り上がります。


Ⅳ.課題と抱負
いまだに和楽器は珍しいとか廃れているといった話を聞きますが、少なくとも私が日本音楽に出会った20年前は稀にしか見聴き(津軽三味線が洋楽器とコラボレーションしていたくらいのテレビや雑誌の情報)する事はありませんでした。今では洋楽器とコラボする事は当たり前になっています。また様々な日本の伝統芸能を主にする方たちも動画などのコンテンツでその存在を容易に知ることができます。1998年文部科学省の指導要領改訂により学校でも(部分的ではありますが)音楽教育に取り入れられました。私の指導する大学のサークルでは、年々和楽器経験者の割合は増えている傾向が見受けられます。演奏人口が増えているかどうかはわかりませんが、国内での音楽のジャンルにおける割合においては増えているような実感はありますし、選択肢の一つとして挙がっているのは確かであると思います。
重要なのは和楽器、ひいては日本音楽が選択肢に挙がっている中で取捨選択された結果どうなっているかどうかです。 日本の音楽は流入文化の取捨選択と消化創出です。奈良時代から伝わる世界最古のオーケストラ「雅楽」や西洋音階との融合「演歌」などが混在する文化です。異文化を取り入れて新しいものを生み出す力と伝統を守るという文化が衝突、あるいは切磋琢磨して進んでいく文化なのだと思います。そのためにはどんどんと異文化衝突を起こし、伝統と新文化、それぞれの進むべき方角(邦楽)へ道筋をつけるのが課題だと思います。
(2022年9月7日公開)
「新しい方角(邦楽)」は日本の伝統音楽の新しい道を探るコラムです。
新しく斬新な試みで邦楽(日本の伝統音楽)の世界に新しい息吹を吹き込んでいる邦楽演奏家の方やその活動などをご紹介し、邦楽の新しい方向性を皆さんと共に模索しています。
「新しい方角(邦楽)」
#コラボレーション